広告(Kindle Unlimited本)
母の名は徹子という。
日永徹子、四十二歳。
手芸や料理といった家庭的な趣味を持つ女性であり、手先も器用で優秀で、大抵のことは人並み以上にこなしてしまう。
ただ、車の運転は最悪。
エンストを何度も起こし、この町に着くまでにいったい何度、事故を起こしそうになったことだろうか。
この母の車にはできることなら乗りたくはない。願わくば、もう二度と……。
「朝子、もうすぐ着くわよ」
信号機が赤色になったからなのか、目を閉じているわたしには分からないが、この車は現在停車している。
だけど、それも数秒のことだ。
時間が経過すれば赤は緑に変わる。そして、それと同時に母は車のシフトレバーに手を構え、慌ただしく操作を開始する。
「何これ?」
母の情けない声とエンジンの音でわたしは理解した。
これはエンストの兆候だ──って痛ッ!!
「おかあさん、わざとやったでしょ」
「違うわよ。私の左腕が暴走したのよ」
何を言ってるんだ、この人は。十四の娘の腹に裏拳を入れて、その程度の謝罪で済むと思っているのだろうか?
母の手はシフトレバーから容易にすっぽ抜け、いい感じにわたしの腹部に拳が直撃した。
ついでに言えばエンジンも止まり、後続の車はクラクションを鳴らしてわたしたちに罵声を浴びせている。
「下手くそが車に乗るんじゃねぇッ!! 邪魔なんだよ、早くどけ」
慣れたものだ。
母は暴言を吐く彼の声に全くと言っていいほど耳を貸さず、なぜかわたしに世間話を振ってくる。
「バイオリンはどうなの? 続けるの?」
「え? あぁ、まあ、趣味程度には……続けるのかな?」
正直、将来のことで色々と悩んでいるわたしではあるけど、今は母が事故を起こさないかどうかで頭がいっぱいだった。
複雑な感情も恐怖と言う強い感情の前では、意外と大したことがないのかもしれない……。
「ふ~ん、そう。あなたの好きなようにやりなさい。人生は一度しかないんだから」
いいことを言っているようにも思うけど、未だに母はエンジンをかけられずにいる。
何度も何度も失敗し、ついには後続のおじさんが車から降りて文句を言いに来る始末。
「おい女! 降りろ」
ああ、おじさんが横窓を叩いてるよ。
これは流石に謝った方がいいのかな?
「うぉっ」
母の声とともに車は突然動き出した。
アクセルを踏み込みすぎたのか、母の車は驚異的な速度で緑の信号をまっすぐに突き抜け、風になった。
そして、窓を叩いていたおじさんは恐怖で腰を抜かして、魂の抜けた埴輪のような顔で虚空を見ている。
可哀そうに。
窓から後ろを覗くと、震えているおじさんの姿が見えた。
「ごめんね、おじさん」
わたしは彼に小さく謝罪をし、今日の出来事は忘れてしまおうと深く思った。
*
潮の香りと、車内に吹き抜ける涼しくて心地よい風。
わたしの目はすっかり冴えて、窓からは朝焼けの空と、日に照らされて輝くオレンジとブルーの海が見えた。
腰を抜かしたおじさんを見送ってから何気なく眺めていた風景だったけど、これほど美しい景観を見ることができたことに関しては、母に感謝をしなければならないだろう。
「おかあさん、おばあちゃんの家まであとどれくらいなの?」
「……」
「おかあさん?」
海岸線の見える道路には母の運転する青いてんとうむし型の自動車が一台。
他には何もなく、あるのは果てなく続く、一本の公道。
先ゆく道はあれども、人っ子一人どころか家の一軒すら建っていない。
そんな道をトボトボと三十キロほどの速度で走らせていた母は、深刻そうな表情で言った。
「地図を出しなさい、朝子」
「えっ?」
「ここ、どこなのよ」
「……おかあさん」
呆れた。
流石に生まれ育った地元なら迷うことはないだろうと思っていたけど、まさかこれほどまでとは……。
「よく免許取れたね」
「いいから出しなさい」
母の態度が気に入らなくて反抗してやろうかとも思ったけど、もう何時間も車に乗っていてわたしの心と腰は悲鳴をあげていた。
──完!!!!!!!!
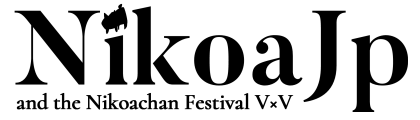





コメントをする(URLは不可).