YouTubeをぼけ~っと見ていると「速読・多読に意味はないです!」とかいう動画が表示される。
曰く、「速読は満足度を高めるだけで意味がない。海外の論文で速読は否定されている」ということなのだが、引用元になった海外の論文を読んでもそんなことは書かれていなかった(どこにあるの!?)。
あと、世の中の人間は海外の論文を信用しすぎている。ちゃんとしたデータのない論文に価値はあるのだろうか。実験に参加した人間の(データの数)はどれほどの規模なのだろうか。そういうことをちゃんと考えるべきなのではないのだろうか。と、僕は思った。
いや、僕もそこまで真面目に調べたわけではない(実際に速読に意味がないという素晴らしいデータがあるのかもしれない)のだけど、「速読・多読に意味がない」という意見は直感的に間違っていると感じる。
広告
・ そもそも速読の定義が謎
中国の少年が1冊の(300ページくらいの)本を30秒で速読する動画があるのだが、アレは明らかに人間のレベルを超越している。
さすがに僕もそんな速読には疑いの感情を抱いているのだが、1.5倍の速度で本を読むことに関してはそれほどの理解度の差は生じないと思える。
動画を1.5倍速にすることで内容が全く分からなくなるなんてことはあるのだろうか? まあ、行間やテンポ感のようなものが得られなくなったりすることはあるわけだが、大枠での理解度は変わらないだろう。
小説なんて文章が多いだけで(情報的な)中身がない。中身がないものをゆっくり読んでも、素早く読んだとしても得られるものは大して変わらないだろう(※ 中身がないというのは文章量に対して情報が少ないという意味であり、世の中の小説を否定しているわけではないです!!!)。
「リアルな経験」を得たいのなら速読・倍速視聴は間違いではあるが、「知識や大枠を理解したい」だけなら速読をすることに問題はないと思う。それについては速読を否定しているといわれている論文にも書かれている。この論文は「速度と理解度はトレードオフの関係にあり、速読は精読に比べて理解度が落ちる」という当たり前の話をしているのだが、なぜかこれが速読完全否定論みたいに引用されている。というか、この論文の読書定義が精読(深い理解)なので一般的な読書理解よりも若干条件が厳しい。また、スキミング(大枠の理解をする速読)については合理的な方法だとすら書かれている(※ スキミングが普通の読み方よりも完全に優れているという意味ではない。場合によっては利点がある技術だと言っている)。
広告
・ 読む時間にこそ価値がある
「1冊の本を1時間読む」と、「6冊の本を合計で1時間読む」なら、後者の方が得られるものは多いと直感的に理解することができる。それが同じジャンルの本なら尚更、後者の方が価値があるだろう。セカンドオピニオンのようなもの。多くの物を読み、比較をすることでより多くのことが理解でき、誤りも減る。
だが、「1冊の本を1時間で読み終える」と、「1冊の本を10分で読み終える」なら、前者の方が価値があると誰でも理解することができる。
ということ(※ 僕の意見)。
広告
・ 遅読も同じ
「本をゆっくり読むことで内容を深く理解できる」というのが遅読なのだが、これも先ほどの話と変わらないと思う。
結局は読んでいる時間だ。1冊の本を1か月かけて読んだとしても、読んでいる時間(本と向き合っている時間)そのものが短いのなら価値がない。
記憶は反復。思考。脳に負荷をかけることで定着をする。
広告
・ 音読と遅読の欠陥
音読は口を使うため、喋るという行為に記憶が結びつく。だから僕は音読をすること(そのもの)は非常に良いことだと思っているのだけれど、「とりあえず音読するか~」みたいな感覚で音読をしても意味がない。
やっぱり、音読をすると文章が頭に入ってきづらい。人間はマルチタスクが不得意なため、意識をしないと「音読をする」というタスクに処理が向かってしまうのだ。
だから、音読や遅読をするのなら、普通に読むよりもしっかりと内容を理解する努力をしなければいけない。それは速読も同じで、「とりあえず文章を全部読むか~」みたいな感覚で読んでしまえば頭に入ってこないのは当然だ。
広告
・ 取りこぼしてもいい
僕も昔は小説が苦手で読めなかったのだが、最近は普通に読むことができるようになった。それは、「取りこぼしを恐れなくなったから」だ。
無自覚の内に小説を神格化していた。
アニメだって1年前に見た内容を完璧に、12話全てを思い出すことができるだろうか? キャラクターの名前とかを完璧に覚えているだろうか。
普通は覚えていない。必ず抜け落ちているものがある。
なのに、「小説はキャラクターの名前を完全に覚えなければいけない」だとか、「この1文を完璧に理解しなければ!」みたいに思ってしまうのはおかしくないだろうか。
「無視をしてください!!!!!(CV:コビー)」
小説を全部読むことにそれほどの価値はない。気軽に読み飛ばそう。
適当に読んで適当に読み飛ばして、気に入ったり理解を深めたかったらもう一度読めばいいのだ。
っていうか、1回読んだだけで本の内容を完璧に理解するなんて不可能だ。学校の教科書なんてだいたい200ページくらいなわけで、文章量だって小説よりも少ない。小説よりも少ないのに、この世の中にいる人間は教科書の内容を全く覚えていないわけだろう? それが事実だ。
「良いんです。速読をしても読み飛ばしてもいいんです!! 100%理解する必要はないんです。もっと気軽に本を読んでもいいんです!!」
速読、気軽にしよう。
YouTubeショートを見るくらいの気軽さで本を読もう。
※ 謎の情報商材みたいな速読術を推奨しているわけではない。速読は「数をこなすことでのみ習得できる術」だと僕は思う。経験による最適化。不要なものを高速で取捨選択する思考能力。なので、速読術を得たいのなら本を沢山読むのがいいと思う。気軽に読もう。
オススメなのはキッズ向けの本。
国語も数学と似ている。基礎を理解できていないと(算数を完全に理解していないと)途中で置いていかれてしまう。
下の(難しくない)レベルから、段階的に読むのが一番賢い。
???「アチャチャチャチャチャチャチャ」
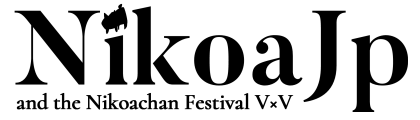

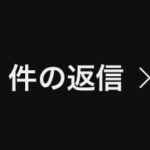




 ニコア(NikoaJp)
ニコア(NikoaJp)
得られる知識の量は
1冊10分×6>1冊1時間>>1冊10分